2050年、蓄電池市場は世界で100兆円規模に拡大すると予測されています。
脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーやEV普及を支える蓄電池の役割はますます重要です。特に次世代技術である全固体電池や革新型電池の開発、さらにNITEとJARIによる安全基準の策定が進み、産業構造は大きく変化しようとしています。
今回は、2050年に向けた蓄電池市場の成長予測や課題、そして企業・自治体・個人に求められる戦略を分かりやすく解説します。
2050年に向けた蓄電池市場の将来性と成長予測

再生可能エネルギーや電気自動車の普及を背景に、蓄電池市場はかつてない成長を遂げると見込まれています。特に2050年には世界市場規模が100兆円に達するとの試算もあり、その将来性は非常に大きな注目を集めています。
まず、経済産業省の予測をもとに、市場がなぜ拡大するのか、どのような要因が成長を後押しするのか、そして今後のシナリオについて詳しく解説します。
世界市場は100兆円規模へ – 経済産業省の試算
経済産業省は、蓄電池市場が2050年には、100兆円規模に達すると予測しています。
この試算は、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出を実質ゼロにする取り組み)の実現に向けて蓄電池の役割が不可欠であることを前提としています。
特に、再生可能エネルギーは発電量が天候に左右されるため、安定供給を支えるためには大規模な蓄電システムが必要です。
また、世界的に電気自動車(EV)の普及が加速しており、車載用の高性能電池の需要も急増しています。こうした需要の積み重ねが、市場を飛躍的に拡大させる要因となっています。
出典:経産省「蓄電池産業戦略(最終取りまとめ)」 / 経産省「参考資料(蓄電池)」
市場拡大の背景にある脱炭素と再生可能エネルギーの普及
蓄電池市場が拡大する最大の理由は、世界的に進む脱炭素化の流れです。
温暖化対策として、各国が再生可能エネルギーの導入を加速させていますが、太陽光や風力は発電量が一定でなく、需給バランスの安定化が大きな課題です。
そこで、余った電力を一時的に蓄え、必要な時に供給する蓄電池の役割が非常に重要になっています。さらに、住宅や企業での自家消費ニーズも高まり、定置用蓄電池の設置が進むことで、家庭やオフィスでも電力の安定利用が可能になります。この動きは今後、世界中で広がると考えられています。
2030年から2050年にかけての成長シナリオ
2030年までに、蓄電池市場は基盤整備期に入り、特に全固体電池の商用化が進むと見込まれます。
全固体電池とは、従来のリチウムイオン電池で使用されている液体電解質を固体に置き換えた電池で、安全性が高く、エネルギー密度も優れているのが特徴です。
2030年代半ばにはEVの普及とともに車載用蓄電池の需要が一気に高まり、2040年以降は中古電池の再利用市場が本格化します。そして2050年には、再生可能エネルギーと蓄電池が主役となる電力システムが確立し、エネルギー供給の安定性が飛躍的に向上すると予測されています。
車載用と定置用で広がる蓄電池の需要動向

蓄電池市場の成長をけん引するのは、大きく分けて車載用と定置用の2つの分野です。
電気自動車の普及に伴う車載用の需要は急増しており、再生可能エネルギーの導入拡大とともに定置用の必要性も高まっています。
次に、それぞれの市場動向と将来の展望、さらに中古電池の再利用による循環型経済の動きについて解説します。
EV・PHV・HEVなど車載用電池のシェアと今後の動き
現在、車載用蓄電池は市場の中心を占めており、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、HEV(ハイブリッド車)向けに幅広く採用されています。
特にEVの普及は世界的に進み、欧州連合は2035年以降、CO2を排出する新車(ガソリン・ディーゼル等)の販売を実質的に禁止する方針を法制化しています。一方、中国は2035年に新エネルギー車(NEV:BEV/PHEV/FCEV)比率50%などの数値目標を掲げており、全面的な販売禁止ではありません。
出展:European Parliament / SAE-China “Technology Roadmap 2.0”
ただ、脱炭素化の流れが強まっているため、その結果、車載用電池の需要は今後数十年で飛躍的に拡大する見込みです。
また、エネルギー密度を高め、充電時間を短縮する技術革新も進んでおり、全固体電池の実用化が普及をさらに加速させると予測されています。
再エネ普及とともに拡大する定置用蓄電池市場
再生可能エネルギーの導入が進む中、定置用蓄電池は電力の安定供給を支える重要な役割を担っています。
太陽光発電や風力発電は出力が天候に左右されるため、余剰電力を蓄え、必要なときに供給する仕組みが不可欠です。特に家庭やオフィスでは、電気代の高騰や停電リスクへの備えとして、定置用蓄電池の導入が増加しています。
さらに、工場や大規模施設における自家消費型システムの採用が進み、蓄電池はエネルギーコスト削減と脱炭素経営の両立を実現する手段として注目を集めています。
中古車載電池の二次利用と循環型経済の推進
EVやPHVの普及により、今後は使用済みの車載用蓄電池が大量に発生すると見込まれています。
こうした電池は自動車に搭載するには性能が不足していても、定置用蓄電システムに転用することで、再利用が可能です。この「リユース」や「リサイクル」は、資源の有効活用だけでなく、環境負荷の低減にも大きく寄与します。
二次利用のための安全基準や性能評価方法の整備が進めば、中古蓄電池市場は新たなビジネスチャンスとして拡大するでしょう。これは循環型経済の実現に向けた重要な取り組みです。
次世代蓄電池技術の進化(全固体電池・革新型電池)
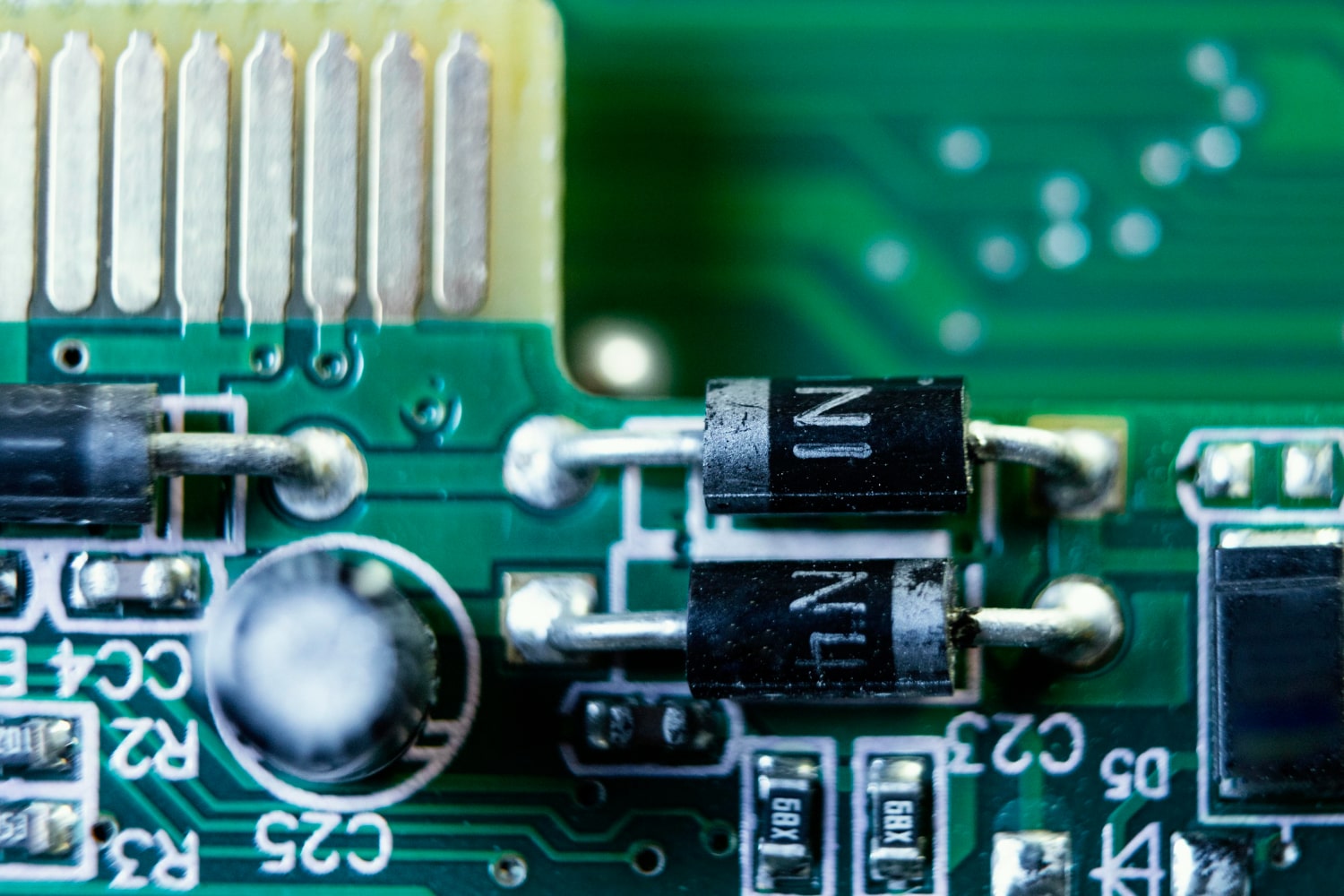
現在主流のリチウムイオン電池は、性能面での課題や資源リスクを抱えており、それを解決するために次世代蓄電池の開発が進んでいます。特に注目されているのが全固体電池と革新型蓄電池です。
これらは安全性やエネルギー密度の向上に加え、安定供給やコスト削減といった面でも期待されています。ここでは、それぞれの技術の特徴と市場への影響を詳しく解説します。
全固体電池の特徴と実用化への期待
全固体電池は、リチウムイオン電池で使われる液体電解質を固体に置き換えた構造を持ちます。
この構造により、発火や漏液のリスクが大幅に低減され、安全性が飛躍的に向上します。また、固体電解質は高いイオン伝導性を実現できるため、充電時間の短縮やエネルギー密度の向上も可能です。
自動車メーカー各社は、2030年前後の実用化を目指しています。トヨタは出光興産と連携し、全固体電池を搭載したBEVの市場投入を2027~2028年に目指すと公式発表しています。日産も2028~2029年頃の量産開始を計画しています。なお、一部サプライヤーは全固体の量産適用に慎重な見方も示しています。
この技術が普及すれば、電気自動車の航続距離や充電性能が格段に向上し、EVの普及を後押しする要因になると考えられます。
出典:Toyota Newsroom / AP News / Financial Times
革新型蓄電池の開発動向と材料革新
革新型蓄電池とは、従来のリチウム資源に依存しない、新しい材料を使った電池技術の総称です。
代表的なものとして、銅や鉄、亜鉛、炭素など比較的安価で調達リスクが低い素材を活用するタイプがあります。フッ化物や塩化物といったハロゲン化物を用いた電池や、亜鉛負極電池なども研究が進んでいます。
これらの開発は、資源確保の地政学リスクを回避しつつ、高エネルギー密度とコスト低減を実現することを目指しています。もしこの分野のブレークスルーが進めば、蓄電池の製造コストは大幅に下がり、エネルギーの安定供給と普及が一気に加速するでしょう。
技術革新が市場規模に与えるインパクト
全固体電池や革新型電池の実用化は、蓄電池市場全体に劇的な影響を与えます。
従来のリチウムイオン電池に比べて、エネルギー密度の向上はEVの性能を飛躍的に高め、再生可能エネルギーの安定利用も可能にします。さらに、調達コストの低減やリサイクル性の改善により、サプライチェーンの安定化にも寄与します。
この結果、2050年に予測されている100兆円規模の市場は、技術革新のスピード次第でさらに拡大する可能性があります。逆に、技術開発が停滞すれば、普及が遅れ市場成長にブレーキがかかるため、今後10~20年は極めて重要な期間といえるでしょう。
NITEとJARIによる安全基準策定と標準化の重要性
蓄電池市場の急成長に伴い、安全性の確保と標準化の重要性はますます高まっています。
特に、全固体電池や革新型電池など次世代技術の普及や、中古電池の二次利用の拡大により、従来とは異なるリスクや評価項目が必要になっています。
続いて、NITEとJARIによる協定締結の背景、その目的、安全評価基準の必要性、さらに技術標準化が産業全体に与える影響について詳しく解説します。
協定締結の背景と目的
2024年7月、独立行政法人NITE(製品評価技術基盤機構)と一般財団法人JARI(日本自動車研究所)は、蓄電池の安全性確保と技術標準化を推進するため、包括的な協力協定を締結しました。
この背景には、急速に拡大する蓄電池市場と、それに伴う新たな課題の存在があります。EVや定置用の蓄電池は、火災や破損などのリスクを抱えており、これらを未然に防ぐためには、科学的根拠に基づく評価基準の整備が欠かせません。
協定の目的は、共同研究や情報共有を通じて安全評価手法を確立し、日本発の標準を世界に広めることにあります。
安全評価基準の整備がなぜ必要か
蓄電池の安全性を担保するためには、製品の性能評価だけでなく、輸送や廃棄、再利用時のリスク評価まで含めた包括的な基準が求められます。
特に全固体電池や革新型電池など、従来とは異なる素材や構造を持つ電池は、新しい試験方法の確立が必要です。
また、中古車載電池を定置用として再利用する場合、劣化の程度を正確に把握し、安全に使えるかどうかを判断する評価手法も不可欠です。基準が不十分なまま市場が拡大すれば、事故や信頼性低下を招き、普及に大きなブレーキがかかる可能性があります。
技術標準化による産業競争力の強化
安全基準や試験方法の標準化は、日本の蓄電池産業が国際競争力を維持・強化するためのカギとなります。
標準化された認証制度は製品の信頼性を高め、国内外の市場で採用されやすくなります。特に次世代電池の分野では、いち早く国際標準を主導できる国が、今後の市場で優位に立つといわれています。
NITEとJARIの取り組みは、日本が世界的な安全規格の策定に関与し、グローバルなビジネス展開を支える大きな一歩といえるでしょう。さらに、標準化によって企業間の技術比較や認証手続きがスムーズになり、開発コスト削減や市場の健全な発展にもつながります。
蓄電池市場拡大に伴う課題と解決策

蓄電池市場の将来性は非常に大きい一方で、その急速な成長にはいくつもの課題が存在します。
資源の安定調達や安全基準の未整備、導入コストの高さといった問題は、今後の普及スピードに大きな影響を与えます。続いて、特に重要な3つの課題と、それに対する解決策の方向性を詳しく見ていきます。
資源調達リスクとサプライチェーンの安定化
蓄電池の主要材料であるリチウムやコバルトは、特定の国や地域に偏在しており、供給リスクが高いことが課題です。例えば、コバルトはコンゴ民主共和国に依存しており、政情不安や児童労働の問題も指摘されています。
また、国際的な需要増加によって価格変動が大きく、企業にとってコスト計画が立てにくい状況です。これに対する解決策として、リサイクルによる資源の再利用や、代替材料を使った革新型電池の開発が進められています。
調達先の多様化や国内生産の強化も、サプライチェーンの安定化に向けた重要な取り組みです。
中古電池の安全性評価と再利用基準の確立
EVやPHVの普及が進むにつれ、今後は大量の中古車載電池が市場に出回ると予想されています。
これらの電池は、定置用の蓄電システムとして再利用できる可能性がありますが、その安全性や性能を正しく評価する仕組みが必要です。
劣化の進んだ電池を無検証で利用すると、発火や破損のリスクが高まり、事故を引き起こす危険があります。そのため、NITEやJARIを中心に安全評価基準や再利用の認証制度を整備する動きが加速しています。
この仕組みが確立されれば、資源循環の促進とともに、コスト削減にもつながります。
導入コストと長期的な投資回収の課題
蓄電池の導入コストは、企業や家庭にとって依然として大きなハードルです。特に定置用システムでは、数十万円から数百万円単位の初期費用が必要となり、導入をためらう要因になっています。
電力料金の削減や環境価値の活用によってコスト回収を図るものの、投資回収期間は10年以上かかるケースもあります。解決策としては、政府や自治体による補助金制度の活用、電力市場における新たな収益モデル(容量市場や需給調整市場)への参入が挙げられます。
さらに、技術革新による電池コストの低減も進んでおり、今後の価格下落に期待が集まっています。
企業・自治体・個人に求められる導入戦略

蓄電池市場が拡大する中、導入を検討する立場は企業や自治体、そして一般家庭と多岐にわたります。しかし、それぞれの目的や課題は異なり、最適な戦略を取らなければ十分な効果を得られません。
最後に、各主体がどのような視点で導入を進めるべきか、具体的な事例やポイントを交えながら解説します。
企業が注目すべき市場トレンドと導入メリット
企業における蓄電池導入は、電力コスト削減だけでなく、カーボンニュートラルやBCP(事業継続計画)対策に直結します。
特に脱炭素経営を目指す企業にとって、再生可能エネルギーと蓄電池を組み合わせる「自家消費型モデル」が注目されています。このモデルでは、太陽光で発電した電力を自社で消費し、余剰電力を蓄電池に貯めて夜間やピーク時間に利用するため、電気料金の削減効果が期待できます。
さらに、電力市場の変動リスクに対応できる点も重要です。2023年以降、日本の電力価格は卸市場で大きく変動しており、エネルギーコストの安定化は企業経営において大きな課題です。
蓄電池を導入することでピークシフトやデマンドレスポンスに活用でき、エネルギーマネジメントの高度化が可能となります。
自治体における再エネ+蓄電池導入の事例
自治体は災害時のレジリエンス強化を目的に、公共施設へ再生可能エネルギーと蓄電池をセットで導入する事例が増えています。
例えば、学校や避難所に太陽光発電と蓄電池を設置することで、停電時にも電力を供給し、地域の防災拠点として機能させる取り組みが広がっています。
加えて、国や地方自治体の補助金制度も導入を後押ししています。
- 環境省「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等の導入支援事業」
- 資源エネルギー庁「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」
この2つが代表的で、補助率が高いため導入コストを大幅に軽減できます。これらの事例は、地域脱炭素の推進と防災力向上を同時に実現する好例として注目されています。
家庭用蓄電池の普及に向けたポイントと補助制度
家庭用蓄電池の普及には、導入コストと経済性のバランスが重要です。
近年はFIT制度終了後の余剰電力買取価格の低下により、自家消費型システムの需要が増えています。家庭用蓄電池を導入することで、昼間に発電した電力を夜間に利用できるため、電気料金の節約に加え、停電対策としても有効です。
また、補助制度の活用も大きなポイントです。国の「住宅用太陽光発電等導入支援事業」や、各自治体の独自補助金を併用することで、導入コストを数十万円単位で削減できます。
VPP(仮想発電所)や電力シェアリングといった新しいビジネスモデルへの参加により、経済的メリットを得ることも可能です。
家庭用蓄電池は、単なる電力貯蔵装置ではなく、エネルギーの最適利用を実現する鍵として位置付けられています。
まとめ
蓄電池市場の成長は、単なるエネルギー技術の進化にとどまらず、2050年のカーボンニュートラル社会実現に向けた基盤整備の一環といえます。
再生可能エネルギーの不安定性を補い、ピークシフトや需給調整を可能にする蓄電システムは、企業や自治体、そして家庭にとって不可欠なインフラとなりつつあります。特に系統用蓄電池の大規模導入は、再エネ比率を高めるだけでなく、電力市場の安定化や災害時のレジリエンス強化にも直結します。
一方で、導入コストや規制、リサイクル問題などの課題も残されています。これらに対応するためには、国や自治体による補助制度の拡充、電力市場の制度改革、企業による新しいビジネスモデルの創出が不可欠です。
また、家庭用蓄電池に関しては、V2H(Vehicle to Home)やスマートグリッドとの連携が進むことで、エネルギーマネジメントの高度化が期待されます。
最終的に、2050年のエネルギー未来は、電力の地産地消と分散型電源の普及を前提とし、蓄電池がその中核的役割を果たします。
今後の技術革新と市場整備のスピードが、日本が世界に先駆けて持続可能なエネルギー社会を構築できるかどうかを左右することになるでしょう。


